児童扶養手当のすべて
離婚後の生活の不安を解消するために、国や自治体の支援制度を最大限に活用することは必須です。
中でも、児童扶養手当は、ひとり親家庭が経済的に自立するために設けられた、最も重要な公的支援です。
1. 児童扶養手当とは?
主に、離婚や死別などによってひとり親になった家庭の子どもの健やかな成長を願って支給される手当です。子どもの生活費を支えるベースとなるものです。
- 対象となる子ども: 18歳になった日以降の最初の3月31日までの子ども(または一定の障害がある場合は20歳未満)。
- 支給時期: 奇数月に、前月分までの2ヶ月分がまとめて支給されます。
2. 児童扶養手当の「支給要件」
次の条件に当てはまる18歳未満(または障害がある20歳未満)の子どもを養育している場合に支給されます。
- 離婚: 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活していない子ども。
- 死別: 父または母が死亡した子ども。
- その他: 父または母が重度の障害者である場合、父または母が生死不明の場合など。
※ただし、子どもが施設に入所している場合や、申請者自身や子どもが日本国内に住所がない場合は対象外です。
3. 最重要!支給額と「所得制限」の仕組み
支給額は、申請者(あなた)の前年の所得に応じて決まります。
手当には「全部支給」と「一部支給」があり、所得が制限額を超えると支給額が減り、さらに超えると全額停止となります。
| 区分 | 支給額(目安) | 所得制限の目安(養育者1人の場合) |
| 全部支給 | 月額 46,690円(子ども1人の場合) | 年収 約190万円未満 |
| 一部支給 | 月額 46,680円~11,010円 | 年収 約385万円未満 |
| 全額停止 | 0円 | 年収 約385万円以上 |
※上記金額は令和7年度(2025年度)の例です。所得制限額は扶養人数によって異なり、給与所得控除後の金額で計算されます。
💡 ゆめママからのアドバイス: 「全額停止だから関係ない」と思わずに、必ず申請してください。所得が増えて全額停止になっても、医療費助成など他の制度の適用を受けるために、児童扶養手当の資格は維持しておく必要がある自治体が多いからです。
4. 申請手続きの流れと必要書類
申請は、お住まいの市区町村の役所(児童福祉課、またはひとり親支援窓口など)で行います。
📌 申請のタイミング
離婚が成立した翌月から手当が支給されます。申請が遅れるとその分手当を受け取れない期間が生じるため、離婚後すぐに手続きをしましょう。
📌 主な必要書類(自治体によって異なります)
- 申請者と子どもの戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
- 申請者と子どもの住民票
- 申請者の前年の所得証明書(または課税証明書)
- 振込先の通帳(申請者名義)
- 健康保険証
- 賃貸借契約書(住居が賃貸の場合)
5. 忘れてはいけない注意点:「現況届」
児童扶養手当の受給者は、毎年8月に「現況届」の提出が義務付けられています。
- 提出の目的: 受給資格の再審査や、前年の所得を確認し、翌年11月からの手当の支給額を決定するため。
- 忘れるとどうなるか: 現況届を提出しないと、11月以降の手当が受け取れなくなります。また、2年間提出しないと受給資格が喪失してしまいます。
💡 ゆめママの体験談: 手続きの際に、担当の方から「公正証書は作成しましたか?」と聞かれました。公正証書がない場合、元配偶者への養育費の請求状況について細かく質問される場合があります。やはり、公正証書は手続きをスムーズに進める上でも重要だと再認識しました。
この手当は、あなたが子どもを守り、自立していくための大切な柱です。手続きは煩雑に感じるかもしれませんが、この記事を参考に、漏れなく申請を進めてください!
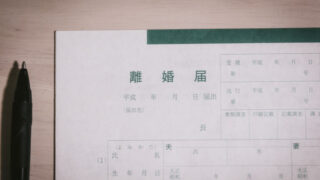

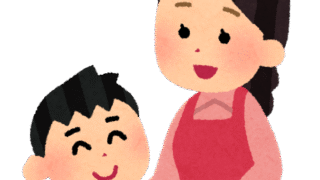


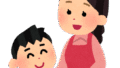
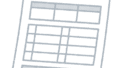
コメント