離婚後の生活基盤を固めるための具体的な一歩
市の無料弁護士相談で法的な知識を得た後、私が次に向かったのは、県や市のひとり親支援窓口(福祉センターなど)でした。
弁護士相談が「法的な道筋」なら、こちらは「生活の道筋」を知る場所です。ここでは、今後の生活に直結する、本当に具体的な支援制度について教えてもらいました。
1. 養育費と公的な証明の重要性
弁護士相談でも話に出ましたが、支援窓口でも養育費の話は最重要視されました。
- 公正証書の作成: 養育費の取り決めを口約束で終わらせず、公証役場で「公正証書」として作成することが強く推奨されました。公正証書は、万が一支払いが滞った際に法的な手続きをスムーズに進めるための、非常に重要な証明書です。
- 離婚方法の確認: 離婚には「協議離婚」と「調停離婚」があること。この方法によって、その後の手続きや時間が変わってくることを改めて教えてもらいました。
2. 知っておきたい!ひとり親家庭の支援制度
お金の不安を解消するために、どんな支援制度があるのかを徹底的に確認しました。
- 児童扶養手当: 18歳までの子どもがいる場合に支給される手当があること。いわゆる母子手当。
- 医療費助成: ひとり親家庭の医療費の自己負担が軽減される制度があること(養育費含めた収入による)。
- 公営住宅の入居: 協議離婚なら離婚後、調停離婚なら申立書の控えがあれば早い段階で市営住宅への入居申し込みが可能になること。住居の確保に悩む私にとって、この情報はとても大きかったです。
3. 子どもの生活と将来に向けたアドバイス
支援員さんは、お金だけでなく、子どもの生活と将来についても親身に相談に乗ってくれました。
- 子どもの姓(苗字): 学校生活では、旧姓のまま通うこともできるなど、子どもの気持ちに配慮できる方法を教えてもらいました。
- 戸籍の選択: 母親と子どもの戸籍をどうするか、母子別姓にする場合のメリット・デメリットについても丁寧に説明してもらいました。
- 就業支援: 「児童扶養手当は18歳まで。その後は正社員で働けていると良い」という現実的なアドバイスもいただきました。これは、私が仕事や資格取得を真剣に考える大きなきっかけになりました。
まとめ:すべての情報は「所得課税証明書」から始まる
この相談で、離婚後の手続きには「所得課税証明書」が何かと必要になること、そして支援金にはレシートが必要になるなど、細かいですが大切な情報も得られました。
福祉センターでの相談は、「誰にも頼れない」という孤立感を解消してくれました。支援員さんの話を聞いて、私は「この制度を使えば、子どもを守りながら自立できる」という具体的な自信を持つことができました。
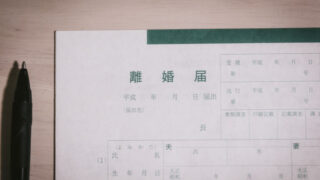

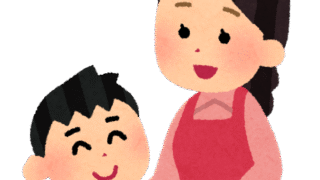



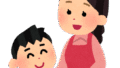
コメント